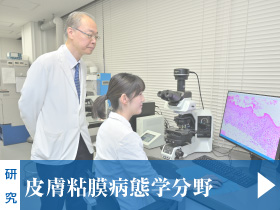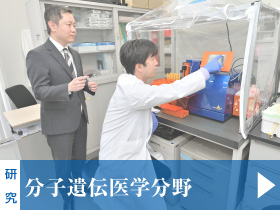生化学・分子生物学(代謝・栄養学)

|
|
生化学・分子生物学(代謝・栄養学)/代謝・栄養学 佐藤 卓 大学院教授 |
私たちの生化学・分子生物学(代謝・栄養学)教室(旧生化学第一講座)は、1936年の創立以来80年以上に亘り、多くの指導的な生化学者を輩出するとともに、臨床から大学院生・研究生を受け入れ、優れた臨床研究者を育ててきた伝統ある教室です。
この長い歴史の中で、当教室は生化学領域における基盤的かつ応用的な課題に取り組むべく、一貫して蛋白質の構造と機能、蛋白質相互作用、先天性代謝異常症の原因解明を軸に、多くの国内外共同研究を展開してきました。当教室が重点的に取り組んできた代表的研究として、(1)先天性骨系統疾患である低ホスファターゼ症における骨石灰化障害の分子基盤解明、(2)金属酵素が関わるレドックス微細構造機能解析と安定同位体アミノ酸ラベル導入用の新規大腸菌発現宿主株コレクション開発・公開、(3)痛風の発症に関わるキサンチン酸化還元酵素キサンチン酸化還元酵素(Xanthine Oxidoreductase; XOR)による触媒反応・活性酸素産生機構、薬剤結合型構造の解明などが挙げられます。特に、XOR研究は抗痛風薬であるフェブリクとトピロキソスタットの開発につながった社会的にもインパクトの大きい研究です。いずれのテーマも、生命現象を分子レベルで理解することを目的とし、基礎生化学の視点を起点としつつ、ヒト疾患の理解やこれらに対する有効な新規治療・予防法の開発へとつながる高い波及性を持つものです。2018年より、前任の大石由美子教授を中心に、これまでの研究基盤を継承・発展させつつ、現代医療が直面する加齢関連疾患や生活習慣病に焦点を当てた研究が展開され、高度オミクス解析や分子イメージングなどの先進技術を用い、代謝恒常性の破綻がどのようにしてこれらの疾患発症に結びつくのかが研究されました。
2023年10月より佐藤が当教室の主宰を引き継ぎ、新たな研究テーマとして、ヒトがんに特化した研究を開始しました。がんは言うまでもなく、現在においても世界的な主要死因の一つであり、その発症や進展に関わる分子機構の解明は、現代医学における最重要課題の一つです。生化学は、細胞内で起こる分子レベルの現象を対象とする学問であり、がんという複雑な病態を根本から理解するうえで、不可欠な視点を提供します。細胞増殖やアポトーシス、エネルギー代謝、さらには細胞間のシグナル伝達といった、がんの本質に関わる生命現象は、生化学的手法による解析なしには十分に語れません。とりわけ近年では、腫瘍細胞における代謝リプログラミングや、特定の代謝酵素の異常発現ががんの悪性化や治療抵抗性に深く関与することが明らかになっており、生化学的アプローチの重要性はかつてないほどに高まっています。
こうした背景を踏まえ、当教室ではがん研究における生化学的アプローチのさらなる深化を目指し、ユニークな研究資源として「患者由来がんオルガノイド」を活用しています。これは、実際の患者の腫瘍組織から樹立された三次元培養がん細胞株であり、従来のがん細胞株と比べ、患者の腫瘍本来の性質を試験管内に忠実に再現できる点が大きな特長です。こうした細胞を用いることで、個々のがんに特有の代謝経路の異常や、薬剤耐性を引き起こす分子メカニズムなど、従来の手法では捉えきれなかった新たな知見が得られつつあります。実際に、患者由来がんオルガノイドモデルを用いた我々の最新研究においては、治療抵抗性と強く関連する特定の代謝経路の変化が明らかとなり、これががんの再発や患者予後に深く関与する可能性が示唆されます(Nakagawa & Sato et al. Commun Biol. 8, 507 (2025), Sase & Sato et al. Dev Cell. 60, 396-413.e6 (2025))。今後もこうしたモデルを用いた研究を通じて、がんの本質に迫る分子レベルでの理解を進め、新たな治療戦略の構築につなげていきたいと考えています。
本学の特色の一つは、臨床と基礎研究との垣根が低く、医学部附属病院との密な連携のもとで研究を進められる環境にある点です。実際の臨床現場から得られる知見や課題を研究にフィードバックし、基礎の成果を再び臨床に還元する「ベンチからベッドサイドへ、そしてベッドサイドから再びベンチへ」という双方向的なアプローチは、本学ならではの強みです。このような環境で行う生化学研究は、単なる基礎的知見の蓄積にとどまらず、実際のがん診療に直結する成果を生み出す可能性を秘めています。
我々は今後も、生化学の視点から様々な疾患の本質に迫る研究をさらに推進し、新たな診断・治療法の開発に貢献することを目指すとともに、次世代の研究者・医療人材の育成にも積極的に取り組んでいきます。